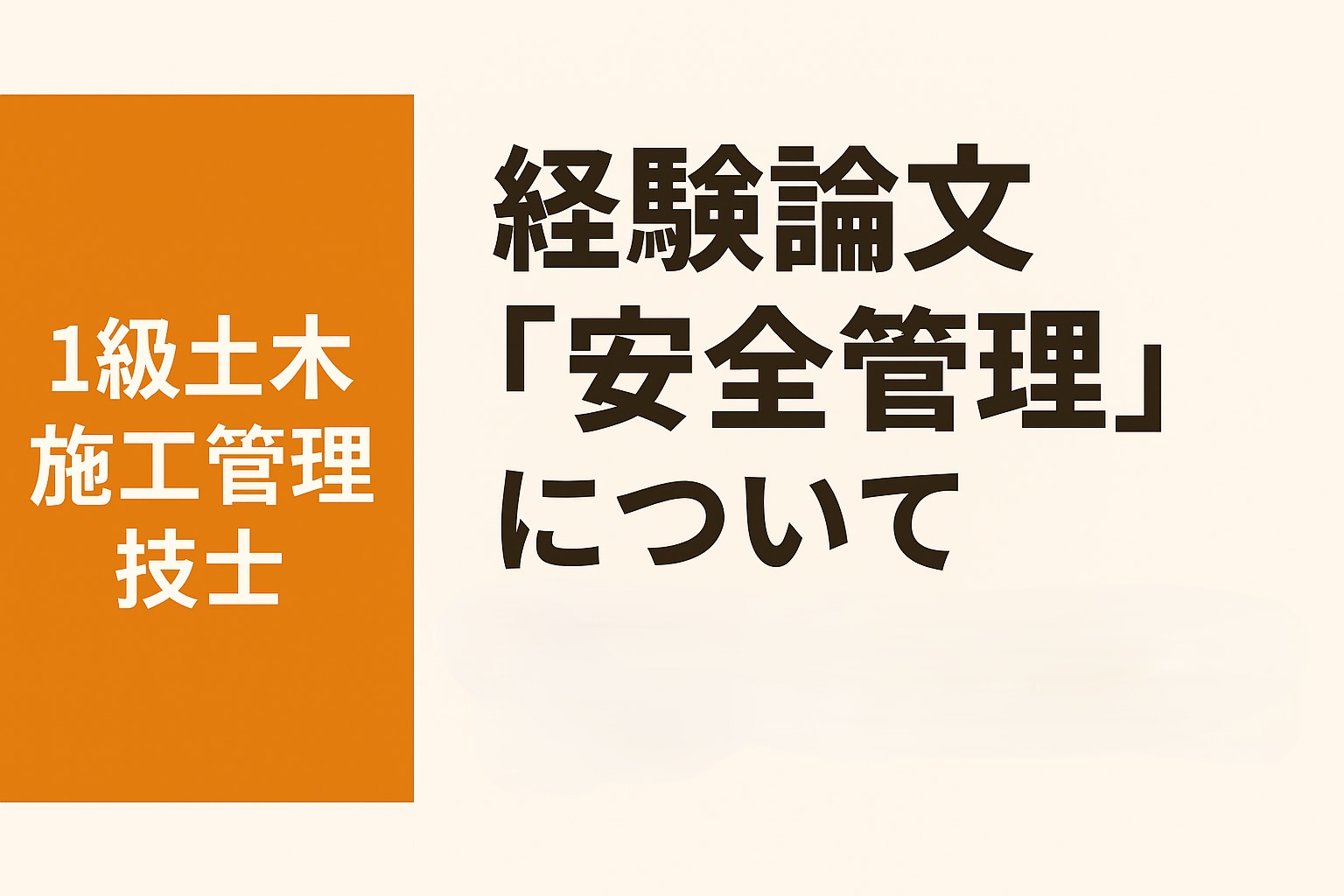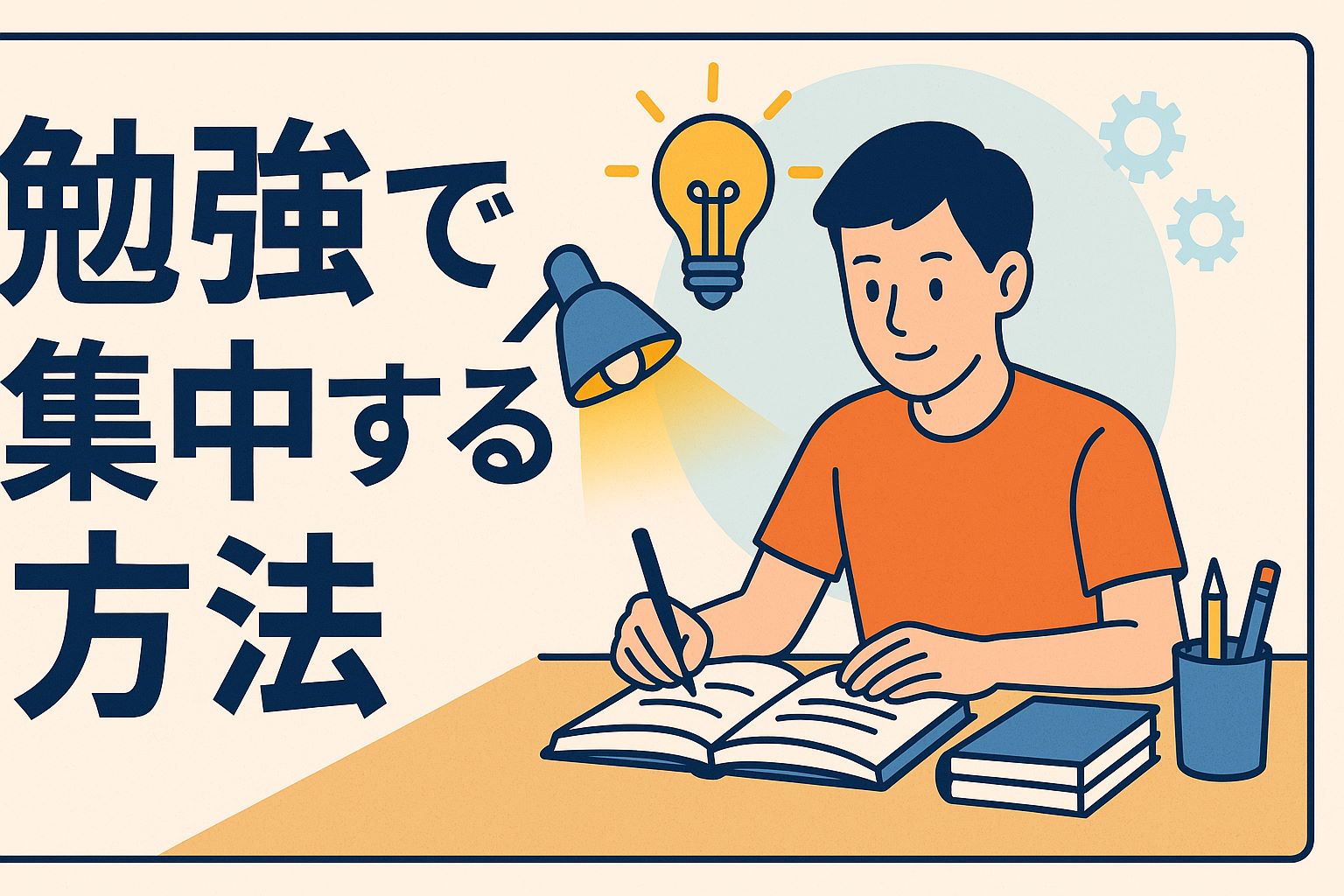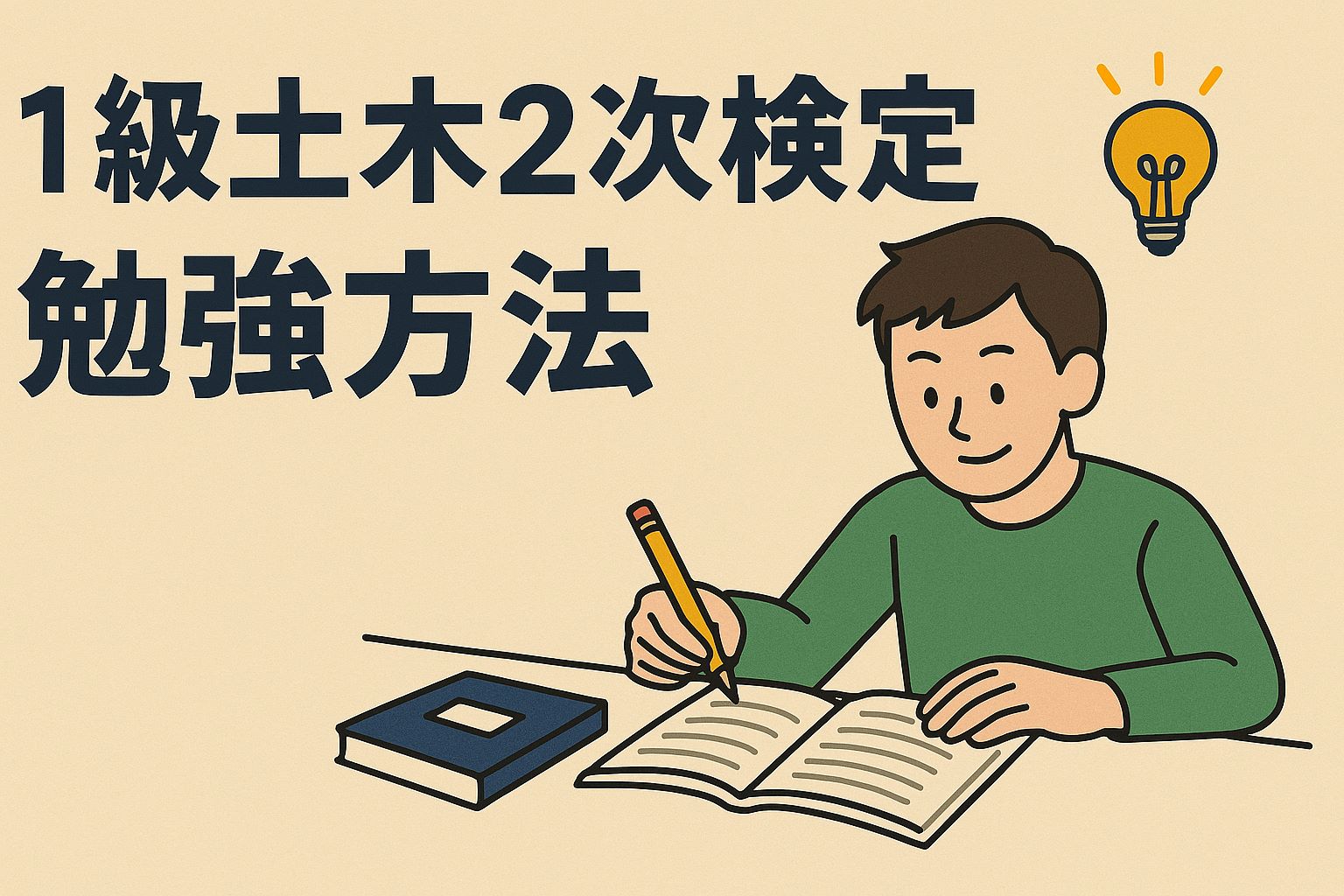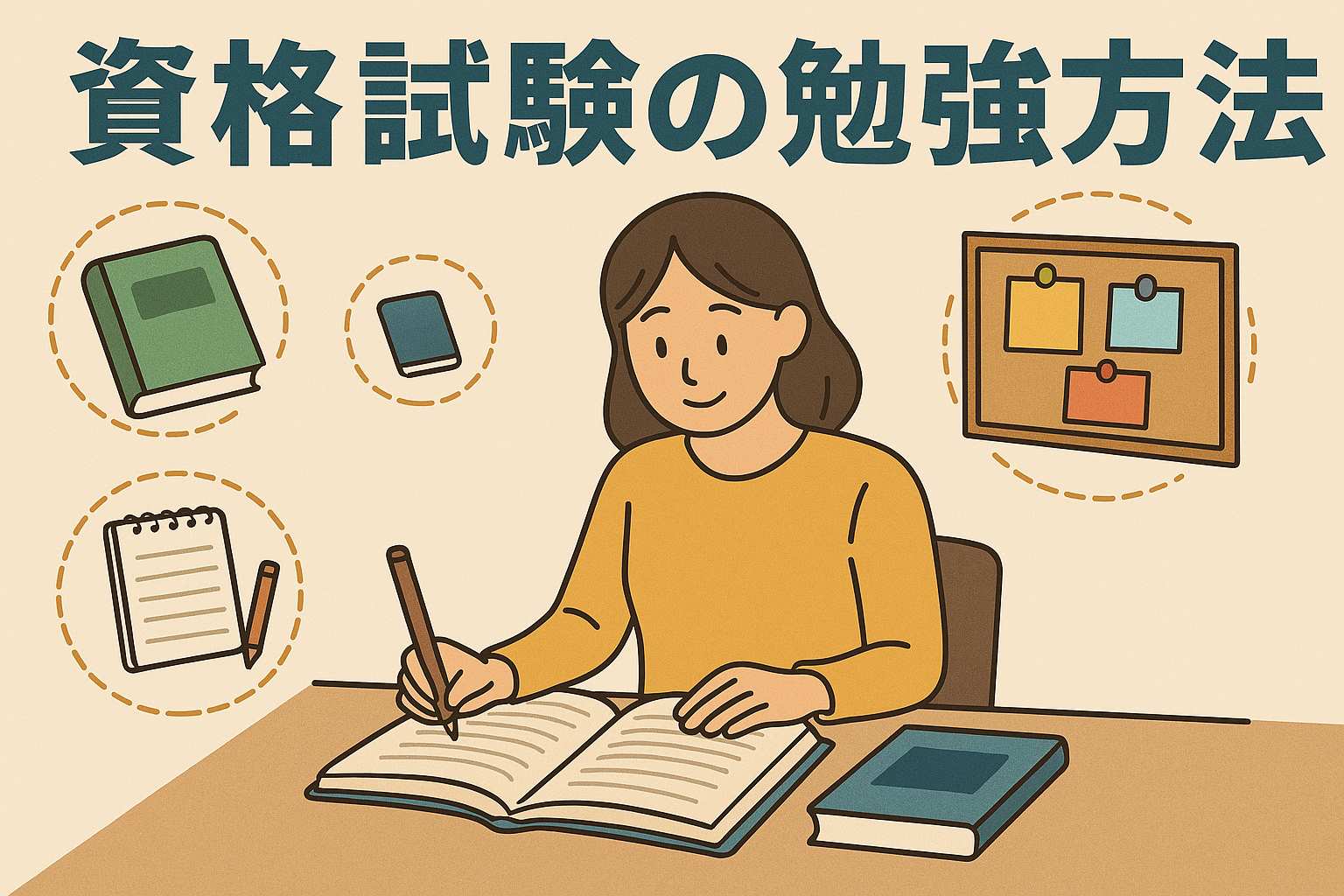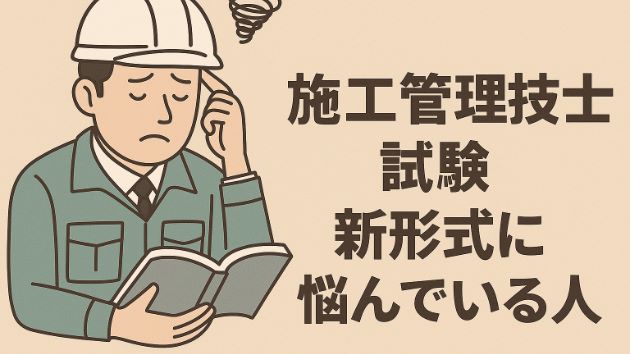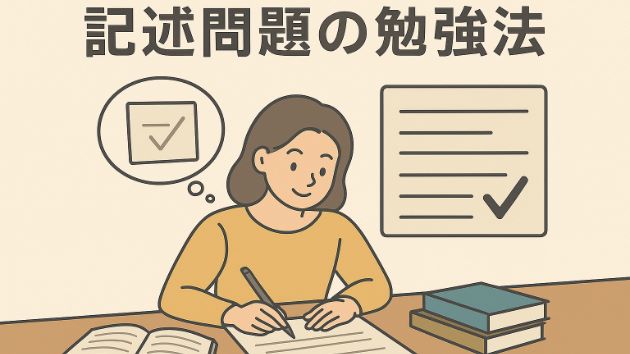施工管理技士 経験論文「安全管理」について
🧱 経験論文とは?
経験論文は、実際に担当した工事現場での課題とその対応策を論理的に記述すものです。1級では、より高度な技術的視点とマネジメント能力が求められます。
📋 論文の構成(例)
設問1:安全管理上の技術的課題
工事現場の特徴(例:交通量、地形、周辺環境)
安全上のリスク(例:重機との接触、落下物、第三者災害)
設問2:課題への対応処置
検討した対策(例:視認性向上、動線分離)
実施内容(例:LEDバリケード、安全ベスト、バックモニター)
効果と成果(例:無事故・無災害の達成)
✍️ 書き方のポイント
1. 現場の特徴を具体的に
例:都市部の交差点付近での下水道工事。交通量が多く、歩行者との接触事故のリスクが高かった。
2. 技術的課題を明確に
例:作業員の視認性が低く、重機との接触事故が懸念された。
3. 対応策は実務に基づいて
例:重機にバックモニターを装着し、作業員には高視認性ベストを着用させた。作業区域にはLEDバリケードを設置。
4. 効果を数字や成果で示す
例:工事期間中、事故ゼロを達成。第三者災害も発生せず、近隣住民からの苦情もなかった。
📝 実例(要約)
本工事は都市部の下水道管布設工事であり、交通量が多く、歩行者との接触事故が懸念された。安全管理上の課題として、作業員の視認性向上と重機との接触防止が挙げられた。対応策として、重機にバックモニターを装着し、作業員には蛍光色の安全ベストを着用させた。また、作業区域にはLEDバリケードを設置し、通行人との動線を分離した。これにより、工事期間中の事故はゼロであり、安全かつ円滑な施工が実現できた。
🎯 合格に近づくためのコツ
・「である」調で論理的に記述する
・土木・施工管理の専門用語を適切に使う
・数字や具体的な名称を入れる
・第三者による添削を受ける
・過去問や合格者の論文を参考にする
🧰 まとめ
1級土木施工管理技士の経験論文では、単なる現場の報告ではなく、「技術的課題にどう向き合い、どう解決したか」を論理的に示すことが求められます。安全管理はどの現場でも重要なテーマですので、あなたの経験を活かして、説得力のある論文を作成しましょう!